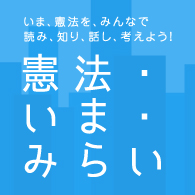最高裁砂川大法廷判決から集団的自衛権を導き出すことはできない
米軍立川基地の拡張に反対する「砂川闘争」(1955~57年)における抗議行動の過程で基地用地内に立ち入ったとして、7人が「日米安保条約に基づく刑事特別法違反」の容疑で起訴されました(→こちらを参照してください)。
この事件における最高裁大法廷判決を「集団的自衛権」行使容認の根拠としようとする動きがあります。この動きに対する批判を「戦争をさせない1000人委員会」事務局長で弁護士である内田雅敏さんから寄せていただきましたので、掲載します。(事務局)
最高裁砂川大法廷判決から集団的自衛権を導き出すことはできない
内田雅敏(弁護士・「戦争をさせない1000人委員会」事務局長)
2014年3月27日付毎日新聞によれば、高村正彦自民党副総裁は、1959年の砂川最高裁判決が「自国の存立を全うするために必要な自衛措置を取りうるのは当然」としているのを引き合いに出して、集団的自衛権に付き限定的な行使は可能だと述べたという。
砂川最高裁大法廷判決は、後に、田中耕太郎最高裁長官(当時)が、最高裁での審理開始前にマッカーサー米大使(当時)と会談していたことが判明し、裁判の公正さが疑われており、又、後述するように、「統治行為論」により憲法判断を回避するなど批判あり、これを金科玉条のものとするつもりはないが、高村氏は、弁護士出身なのだから、判例の引用は、該箇所がどのような文脈の中で語られているかを正確にしなければいけない。高村氏が引用する判例の該箇所は以下のとおりである。
「わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである。憲法前文にも明らかなように、我ら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうち位に生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうることは国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずる我が国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全保障等に限定されたものではなく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式または手段ある限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであって、憲法九条は、わが国が平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである」(【注1】)。
上記文言から、「わが国に対する攻撃でなく、わが国と密接な関係のある他国に対する攻撃に対して」わが国の自衛隊が他国の軍隊と一体となって行動する集団的自衛権を導き出すことはできない。そもそも、判例の上記文言は、わが国が自衛権を有することは当然としつつも、後述するように、憲法第9条の下で「自衛戦力」を有することができるかどうかはさておき、としているのである(【注2】)。
砂川事件裁判で最大の争点となったのは、在日米軍が憲法第9条2項によって保持を禁じられている「戦力」に該当するかどうかということであった。一審の東京地裁伊達判決は、在日米軍は憲法第9条2項が禁ずる「戦力」にあたるとして在日米軍の存在根拠である日米安保条約は憲法違反、したがってこれに基づく刑事特別法も憲法違反として、起訴された7名の学生に無罪判決を言い渡した。
ところが検察側からの跳躍上告を受けた最高裁大法廷は、この無罪判決を破棄し、被告人らに対し逆転有罪の判決を言い渡した。判決は憲法前文中に「日本国民は・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持しようと決意した。」とある点に注目し、日本は憲法第9条2項によって「戦力」を持つことができないが、しかしとして、
「われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである。・・・憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである」
と前記のように述べた上で、
「右のような憲法9条の趣旨に則して同条2項の法意を考えて見るに、同条項において戦力の不保持をも規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする。従って同条2項がいわゆる自衛のための戦力の保持を禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」
と述べる。
在日米軍は日本政府の指揮管理下にないから、憲法第9条がその保持を禁ずる「戦力」に該らないというのである。
何故、指揮管理下になければ、憲法の禁ずる「戦力」に該当しないというのか全く理解できない。また「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」というのも伊達判決が指摘するように国際連合を指すと解するのが無理のない解釈だと思う。大法廷判決は、さらに、「(日米)安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」と、悪名高い「統治行為論」を述べ憲法判断を回避した。
それから半世紀を経た今日もなお日本の裁判所は、この「統治行為論」の呪縛から抜け出ることができていない。自衛隊の装備の拡充、米軍との一体行動は当時と比べて格段に強められているにもかかわらずである。
なお、集団的自衛権に関連する箇所として、最高裁大法廷判決において田中耕太郎(長官)が以下のような補足意見を述べていることに注意を払う必要がある。
「一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的に即ちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち『他衛』、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。」
要するに、今日においては個別的自衛権、集団的自衛権の区別はもはや意味がないと言うのである。今日、「テロとの戦い」が声高に語られる。《テロリストという非対称的な「敵」は、何処にいるかもわからない》、《何処でテロが起こるかもわからない》、《テロとの戦いには個別的自衛権も、集団的自衛権もない》、《テロ組織の居場所が分からないから、テロとの戦いには講和ということはなく、相手を殲滅するまで戦いは続く》、等々である。テロを生む土壌が放置された、対症療法としてのテロとの戦いには終わりはない。「テロとの戦い」国内を不断の臨戦態勢(種々の人権制限がなされる)に置くためのマジックカードである。前記田中耕太郎の補足意見、「今日では自衛即他衛、他衛即自衛」は今日の事態を先取りしたものではなかったか。
【注1】 砂川大法廷判決は、憲法前文にいう「平和的生存権」、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」に依拠して、日米安保条約、在日米軍の憲法適合性を説明し、また、判決冒頭部分において、「そもそも憲法第九条は、わが国が敗戦の結果ポツダム宣言を受諾したことに伴ない、日本国民が過去におけるわが国の誤って犯すに至った軍国主義的行動を反省し、深く恒久の平和を念願して制定したものであって」と、日本国憲法の出自についても述べる。自民党の改憲草案が憲法前文を目の敵にし、前記文言および憲法の出自について、これを削除しておきながら、集団的自衛権行使容認を裏付けるために、砂川大法廷判決を持ち出すのは、不思議というしかない。そもそも、憲法上、集団的自衛権行使は容認されないとする歴代の政府見解(内閣法制局)は、砂川大法廷判決を前提にしたものではなかったか。
なお、憲法の前文については、単なるプログラム規定であって、これを具体化にする立法があってはじめて法規範性を有するという見解もあるが、このように、最高裁自身が重要判例で、直接、前文に依拠しているのである。
【注2】 小泉首相(当時)が国会の委員会で、自衛隊が合憲なことは、最高裁も認めているところだと述べたことがあったが、最高裁は「自衛戦力」を有することができるかどうかは「さておき」としたままで、その後も、自衛隊の合憲性の有無については判断していない。このように、自衛隊は、社会的にはともかく法的には今日に至るまで認知されてはいないのである。
同じカテゴリの記事
- 2025年4月18日
新しいチラシ「どうかんがえる? 石破政権」ができました
- 2024年10月30日
【戦争させない1000人委員会東京南部】映画「戦雲」11.23上映会
- 2024年10月14日
【コラム】主権者として政治に意志を示しましょう